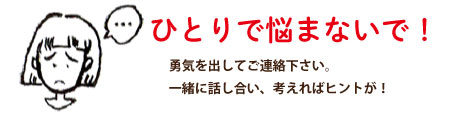お問い合わせをお待ちしております
TEL. 00-0000-0000
営業時間 AM10:00 ~ PM20:00
コラム コロナ禍に想う
◆フイド・フィールドの向こうに
※特集。フイド・フィールドの向こうに(田原 和宏専門記者) 2023・2,16
下橋邦彦記す
*田原記者は、スポーツ全般をカバーしているベテランの記者だ。スポーツにあまり詳しくない私は、目は通すがあまり取り上げる気持ちになる記事に出くわさなかった。が、きょうの論説は価値ある文だ。
以下、まず全文を写しながら、少しだけコメントをつけていこう。
○
――スポーツ界でいうなら、米大リーグの大谷翔平選手(28)=エンゼルス=だろうか。ゆるぎない信念で新たな地平を切り開いただけでなく、その笑顔で多くの人々を魅了し続けることにおいても。
東京大安田講堂で、昨年のノーベル医学・生理学賞に輝いたスバンテ・ペーボさん(67)の講演があった。独マックスプランク進化人類学研究所長のペーボさんは絶滅した人類の遺伝情報を解析する技術を確立し、古遺伝学という新たな学問分野を開拓。ネアンデルタール人の遺伝子を世界で初めて解読し、「我々はどこから東たのか」との問いに迫る研究を続ける。
講演では、途切れることなく続く質問に気さくに答えた。自らを突き動かすものは「好奇心」、子どもの頃に読んだ本は「クマのプーさん」、仕事で大切なのは「何でも言い合える雰囲気」――。
《もうここまで読んだだけで、胸がわくわくしてくる。一人研究室に開じこもって、実験や研究に勤しんでいるイメージとはほど遠い。気さくにお互いの好奇心の網に引っかかってくるものに関心をむけ、同僚や研究社仲間と議論し、それを自分の肥しにしていく。そうした研究者としての姿勢に共感を覚えるのだ》
先に引用したペーボさんの語りから記者の田原さんは、「思わず大谷選手を連想した」という。なぜか?
「どうすれば先生のようなパイオニアになれるか」と聞かれ、ペーボさんはこう答えからだ。「楽しいと思うこと、本当に関心があることを追求してください」
(これを聞いた田原さんは)大谷選手がまさにそうだ。岩手。花巻東高校時代にプロ野球を経由せず、直接大リーグ入りを考えたのも「パイオニアになりたい」との思いからだった、日本ハムはその夢を否定せず、「夢への道シルベ」と題した詳細な資料を提示。データに基づき、国内で地力を磨くことが得策だと説いた。「二刀流」という新たな目標も提案し、翻意させることに成功した。
投手か打者に専念するのが当然だった現代野球に、大谷選手は新たな物差しを持ち込み、周囲の認識を変えた。大リーグでは昨年、 ドラフト1巡目で指名される二刀流選手も現れた。大谷選手を間近で見つめる球団広報のグレース・マクミナーさんは「不可能を可能にできると学んだ。人事なのはプロセスを楽しむこと」と話す。
我々の祖先である現生人類は6万年前以降、アフリカを飛び出した。欧州やアジアに移り住み、ベーリング海峡を渡って米大陸に到達。世界各地へと進んだ。
なぜネアンデルタール人は滅び、我々が生き残ったのか。環境への適応力か言語か、それとも単なる運か。科学者であるベーボさんは「まだ分からない」と語ったが、その答えは「未知への好奇心」と思えてならない。開拓者精神に満ちた2人の姿も、そこに重なって見える。一―
「私の辞書に不可能という言葉はない」と豪語したのは、あの世界制覇を夢見、武力で土地と人を支配し、「あわや」というところで、自然の猛烈なしっぺ返しで、その夢も潰え去ったナポレオン。ジンギスハーンも世界の覇者を夢見て、広大な土地をわがものにしようとしたが、ついにその野望は頓挫した。要は、「武力」「野望」では、いっとき達成された感があっても、いずれも夢を叶えられずに破れていく。
その苦い教訓をまえに、私たちは地道に積み重ね、コツコツ努力し、「夢を夢で終わらせない」そのとてつもない目標をわが手に引き寄せる「ひたむきな努力」と「楽天性」こそが大事なのだと、ペーボさんや大谷選手が私たちに身をもって教えてくれているのだ。私たち年配の世代は、「まさか二刀流とは」の驚きの渦中にある。不可能と思われたことを、実地に実現していくその努力と、自分を取り巻くひととの協和。これこそが、眼前で多くの人が抱く「夢」を実現していっているのだ。 しもはしくにひこ記す
※戦火の町に再び音楽を~ウクライナの交響楽団指揮者・高谷光信さん2023・2・16毎日新聞
(先の田原記者の「フィールドの向こうに」の記事のすぐ左に、大きな紙面で取り上げられた)
コロナ禍3年が経つ2023年。この3年間がひとびとの健康、気持ち、生活状況をどのように変えていったか。そして、どうすればその陥った状況から立ち直っていけるか、その道じるべになるものは何か?
2年目になるウクライナ戦争。つい最近起きたトルコ・シリアの大地震。懸命の救援作業が日々伝えられている。核使用をたえずちらつかせるプーチン。ロシア大統領による扇動に負けじと、ウクライナの学校ではシェルターヘの避難訓練が行われているという。
コロナ禍2年目に入った昨年6月、私は次の文章を書いて、近くの人に伝えてきた。
《ひとは何によって生きていけるか?~戦争下・コロナ禍の暮らしを生き抜く知恵とは》という文章だ。
それから半年余りが過ぎた。上に書いた事態は、ほとんと変わらずある。そのうえ、格差社会がより深刻にな移につれて、さまざまな犯罪がひろがり、いつ何時被害が及ぶかわからない不安に人々を落とし入れている。
先に挙げた昨年6月の文章で、結論を言えば、「芸術。文化こそがひとを救うのだ」ということだった。
その文章では、多くの活躍する文化人・芸術家を取りあげていた。振り返ると次のような人たちだ。
*まず、新国立劇場オペラ芸術監督 大野和士さん
*次に、キュレーター・美術評論家の飯田高誉さん
*文明は野蛮の対極にあるのでなく、文明こそ野蛮との親和性があることを見事に浮かびあがらせた、ドイツの哲学者・アドルノ(ホルクハイマーとの共著『啓蒙の弁証法』にて)。
*また、「文明」と「野蛮」を対立する構図で捉えず、多様な方法論と知性を用いて人間に内在する自己矛盾を浮かびあがらせた旧ドイツ出身の画家、グルハルト・リヒター(以上2項目は、飯田さんの文章から)
*もう一人の論者=彫刻家・評論家の小田原のどかさん
*つづけて今春(2022年)東京芸術大学学長を6年間務め退任したバイオリン演奏家。指揮者である
澤 和樹さん 「社会に音楽は必要不可欠」
*もう一人、「ひと」欄で紹介された芸術プロデューサーの西尾智子さん
*そうして、もう一人何としてもその活動を紹介したい指揮者がいる。それは、若き指揮者。高谷光信さんだ。
「チェルニヒウに戻る日を待つ日本人指揮者」として紹介された。戦火のウクライナから一時的に避難する形で日本に戻ってきている。が、首席指揮者。アンドレイさんと今もショートメセージでやり取りしている。
ヤヌコビッチ政権批判の高まりの中で、練習を重ねていたドボルザーク「新世界より」の演奏が中止となる。バースタインの指揮で練習していて、第4楽章に移ったとき、最年長のチェロ奏者が突然声を上げて泣きだす。どうしたのか、演奏が止まるなかで、彼は「こうして……、こうして、ずっと音楽をしたいんだよ~」と。その声が、今も指揮者の高谷さんの胸に響き続けているというのだ。
*最後に私(シモハシ)がどうしても逃せない存在として挙げたのが、バイオリニスト・前橋汀子さん。
今もつづくロシアによるウクライナ侵攻によって、チャイコフスキーやラフマニノフが聴けなくなるなんて、こんな悲しいことがあっていいのかと、前橋さんは声を絞り出す。そう、音楽は国境を越え、人びとの胸を打つ。その音楽を世界の音楽愛好者から取り上げることは誰にもできないし、してはならないのだ、と。
○
以上の引用。記述から半年余りが経った。今は2023年2月半ば過ぎ。あの指揮者の高谷さんは、キーウに戻れただろうか、そこで指揮をされているだろうかと。その私の思いに応えるかのように、2023年2月16日の毎日新聞夕刊に高谷さんの記事が大きく出たのである。まさに待ち焦がれた紹介記事だ。
見出しは【戦火の町に再び音楽を】その記事のリード文は次のように書かれている。
==「演奏会が開けたんです、ほら」。ウクライナのチェルニヒウ。フィルハーモニー交響楽団常任指揮者、高谷光信さん(45)が1枚の写真を見せてくれた。同フィルが昨年11月19日、ロシアによる侵攻後初めて開いた演奏会の写真だ。日本でウクライナの音楽家の支援を続ける高谷さんの胸の内を聞いた==
書き手は例の小国綾子記者だ。以下、書き写していきたい。
○
写真の中の演奏者はわずか20人足らず。女性が多い。「侵攻前、楽団員は40人以上いました。今は避難先から戻った人を入れても10人ちょっとです。バイオリンは6人が兵士になった。ホルン、 トランペット、コントラバスも。打楽器は全員が戦場に行ってしまった」。(こんなふうに高谷さんが語るのを聞くと、戦争が遠い日本にいる私たちにも具体的に迫ってくる)侵攻から1年、東京都内のホテルのラウンジで、高谷さんは今の同フィルの様子を淡々と語った。
一―チェルニヒウ。フィルの指揮者3人のうち、音楽監督のエコライ・スーカツチさんはパリに避難中。親友で首席指揮者のアンドレイ・シェプコービチさんは昨年4月に志願兵となり、今は戦闘の激しい南東部にいる。「空襲警報と停電の続く戦火の町で、お客さんだって何人集まるか分からない。それでも彼らは音楽をあきらめない。指揮者のいない中、コンサートマスターが指揮をしてくれているそうです」。そう言うと、悔しそうにうつむき、つぶやいた。「僕が行ければいいのに……」。外務省は危険レベル4の退避勧告を出し、ウクライナヘの渡航はやめるよう呼びかけている。・・。(高谷さんの経歴を紹介したあと)コロナ禍とロシアによる侵攻で、ウクライナに行けないまま3年が過ぎた。
(ここで、記者は事実を語っている。が、音楽家。指揮者として3年のブランクは、もしかすると取り返せない3年かもしれない。)このあと、この記事は、次のことを記している。
―一昨年10月、南部の都市ヘルソンの劇場の音楽監督で指揮者、ユーリイ・ケルパテンコさんがロシア軍の兵士に撃たれた。46歳だった。ヘルソンは昨年9月、ロシアにひとたび併合された。報道によると、ケルパテンコさんはロシアを礼賛する演奏会で指揮をしろと軍に命じられたが拒み、射殺されたという。
(いかに理不尽な暴虐をロシアがやっているか、このケルパテンコさんの事実が示している)
彼は、高谷さんと「指揮科の同級生でした」と。クラスは違っても、互いの存在は知っていた。「指揮者同士は意識し合う。『日本から面白いヤツが来たぞ』と他のクラスから指揮科の学生が集団で僕を見にきた。彼はその中の一人。スラブ音楽の精神を学んだ仲間です」「なぜ彼は殺されたのか、高谷さんは思いを巡らせずにいられない。「彼の気性を考えれば、ロシア軍の怒りを買ってしまったのではないか。『侵略者には協力しない。私が指揮するのは、自由を希求するための音楽だ』と皆の前で言ってしまったのではないか」。なぜなら高谷さん自身も音楽院でそう学んだからだ。
「ロシアの圧政に苦しみ、13回も母語を奪われた国だからこそ、国立の青楽院は『自由への希求』というスラブ音楽の精神を最も大事にした。卒業生はウクライナ各地に派遣され、音楽を通し、人びとにその精神を伝導する役目を負っていた。僕は北部のチェルニヒウ、彼は南部のヘルソンで」(二重線。太字はシモハシ)
併合前、町から逃げた音楽家は少なくなかったが、ケルパテンコさんは残った。ヘルソンは彼の生まれ故郷だった。「彼は誇りを持って、自分の町の音楽監督であり続けたんです」
日本にいて、自分に何ができるのか一―。高谷さんは悩み、模索し続けてきた。昨年4月、親友の首席指揮者のアンドレイさんから、無料通話アプリでこんなメッセージが届いた。(敵を監視するためのドローンが必要です。購入し、送ってくれませんか〉。その末尾に、 ドローンの型番が二つ並んでいた。
「悩みました。いちるの望みをかけたメッセージだと、り需いほど分かった。でも、僕は断るしかありませんでした」。だから精いっぱい正直に返事した。(僕が支援のために集めたお金は、武器ではなく、音楽ホールの修繕やピアノを買うことに充てたいのです〉
アンドレイさんも分かってくれた。その後も定期的に連絡を交わしている。昨年10月、高谷さんは祈る思いでこんなメッセージを送った。「戦況が厳しいと聞いたが、絶対に死なないでくれ」
約2時間後、自分の送ったメッセージをアンドレイさんが読んだことを意味する「既読」のマークが表示された瞬間、高谷さんは心で叫んだ、「よかった。彼はまだ生きている!」
2日後、ウクライナ語で返事が届いた。「メーネ。フセ。ドープレ」(こちらはすべて大丈夫)。
高谷さんはそれを私に見せながら言った。「アンドレイはいつも優しい。僕に心配させないよう、メッセージに必ずこの文章を書き添えてくるんです」
高谷さんは今、一般社団法人「日本ウクライナ音楽協会」の代表として、ウクライナの音楽家への支援を呼びかけている。チャリティーコンサートの売り上げや企業・個人のからの寄付金など約100万円のうち半分を既に、国立ハルキウ音楽院に送金した。残りはチェルニヒウ・フィルに届ける予定だ。
活動がネットで批判されたこともある。「音楽で命が救えるか」「今ウクライナの人が求めているのは楽器ではなく武器」だと。しかし高谷さんは言う。「音楽で命が救えるかと問われれば、残念ながら救えません。でも、停戦を実現し、人びとが戦争の傷痕から立ち上がろうとする時、音楽や芸術は必要です」
(この強い信念があるからこそ、日本にいてもできる支援を考え、必要な資金をつくり送り続けているのだ)
ここからは縦見出しで「日本から支援続け」と。
―‐高谷さんは侵攻後も、ロシア人作曲家の作品を演奏し続けてきた。ロシア人作曲家の作品を排除することは、芸術家が戦争に加担するのと同じではないか、と考えた末の選択だ。
しかし、ウクライナを思う時、自問せずにいられない。「ウクライナに帰れた日、僕はチャイコフスキーやラフマニノフを彼らと演奏できるだろうか」。ロシア人作曲家の作品を演奏したくない人もいるはずだ。
「僕がロシア人作曲家の作品をやろうと言った時、楽団員は受け入れるだろうか」。何度考えても答えは「ノー」だ。
「なぜなら殺された人が多すぎる。……」。高谷さんはしばらく沈黙し、言葉を継いだ。「戦争の傷痕を癒やすのに20年、30年とかかるでしょう。それでもいつか楽団員が心からチャイコフスキーやラフマニノフを演奏し、ウクライナの人が感動の涙を流せる日のために、僕は僕の指揮者人生を投じます」
使い込まれた皮表紙のスケジュール帳を見せてもらった。9月4日から15日までの欄に「ウクライナ演奏会」と鉛筆書きの文字がある。高谷さんは予定を書き込まずにはいられなかったのだろう。「もしも9月の時点で停戦がかない、退避勧告が解除されたなら、僕は必ず行く」
丁寧に書かれた「ウクライナ」の文字に彼の痛切な思いと信念がにじんでいるようで、私は胸が熱くなった。高谷さんが今一番ほしいのは、停戦。そして平和だ。 【小国綾子専門記者】
《書写をしながら、私下橋は何度も手を休め、高谷さんの胸の内を反すうしながら、また書写をし続けた。こんなにも書き写すことが難しいのか、写しながら私は、日に溜まってくる涙をぬぐうこともせず、ひたすら高谷さんの心情に寄り添おうとした。しかし、それがなんの力にもならないことを、私自身分かっている。が、写さずにはいられない衝動で私を突き動かして、ここまできた。》
◆お世話になった「コリアボランティア協会」
◆国立療養所栗生楽泉園 藤田三四郎 様
◆一度は出かけたかった「近つ飛鳥博物館」へ~先人の偉大な知恵と暮らしの営みに脱帽する貴重な体験~
◆徳之島は別天地だった
◆身体の記憶をたどる旅
◆「教師駆け込み寺・大阪」趣意書より
お問い合わせはコチラへ!
![]() 電話: 090-5256-6677
電話: 090-5256-6677
![]() E-mail:sonen1939@s4.dion.ne.jp
E-mail:sonen1939@s4.dion.ne.jp
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。