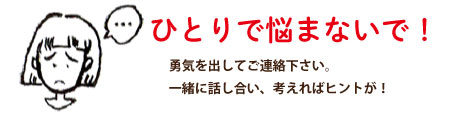お問い合わせをお待ちしております
TEL. 00-0000-0000
営業時間 AM10:00 ~ PM20:00
教師駆け込み寺主宰下橋邦彦が執筆する連載が始まりました
◆教師駆け込み寺から
毎日新聞3月24日の朝刊に、4月からの新企画・継続欄の紹介記事が出た。そのページの左上、【関西発 待望新連載】として、「憲法生活~雨宮さんが現場を歩く」のすぐ下に、標記の「教師駆け込み寺から~下橋邦彦さんが解く」の紹介記事が出た。髪の毛が相当に寒々とした、夏服姿の下橋の顔写真のすぐ後に、『いじめや体罰をはじめ、学校のなかではさまざまな問題が起き、教える立場、学ぶ側双方に悩みが尽きません。土曜(隔週)の教育新企画として、元高校教師の下橋さんが、学校の先生たち固有の悩みについて応え、事例に基づいて解決の道を探る「教師駆け込み寺から」が始まります。』と、新企画の趣旨が書かれている。その第1回が「同僚の助言に救われ」という題で掲載されたのが4月13日だった。第2回は4月27日に「先入観を持たずに」の見出しで掲載されました。
○
連載第1回でもすこし触れたが、今の大阪の学校・教師たちが置かれている状況は、あまりにも過酷だ。その根源は、選挙で選ばれたら何をしてもいい、何を言っても文句は言わせないとする強権的体質の為政者の「政策」、というよりその物言い、一方的な判断による権力の乱用としか言えないやり方によって、「物言えば唇寒し」といった雰囲気を醸し出している処にある。日本全体そして大阪の街を分厚く暗雲が垂れこめている。「政治が教育に直接介入してはならない」という大原則などまったくわきまえない、時の政権に従ってもらうというその態度が学校・教師を苦しめていることなど「想定外」らしい。
○
大阪の教師の賃金は全国一低い、教師の夏休みは「学校五日制」正式発足後なくなった、実労働時間は1日優に14時間を越えている、いくら残業しても「4%」の手当以外に支払われない、教育委員会が催す研修以外は「出張」として認めない・・・その他、あげればもっともっと、大阪を始めとする「劣悪な条件」が、いっそう教師の仕事を困難にしている。こうした「実態」は、為政者には見えないのか、見ようとしないのか。
それでも目の前の「児童生徒」に向き合い、寄り添っていく教師の教育活動をやめるわけにはいかない、やめるどころか「課題」は山積していく故に、ますます仕事に追われ、体も心も疲弊していく。各学校平均3~4人の教師が休職に追い込まれ、その予備軍が多数存在する。それでも、先生方は元気に笑顔で児童生徒らへの取り組みを進めていかなければならない。そうした学校・教師になんとか元気を出してもらいたい、その思いで書きつづけていきます。読者からの反応を受けとめながら、取材をかさねていきます。
下橋邦彦さんが解く
いじめや体罰をはじめ、学校のなかではさまざまな問題が起き、教える立場、学ぶ側双方に悩みが尽きません。土曜(隔週)の教育新企画として、元高校教師の下橋邦彦さんが、学校の先生たち固有の悩みについて応え、事例に基づいて解決の道を探る「教師駆け込み寺から」が始まります。
そして、中・高校・大学生たちは、日々報道されているニュースについて、どう受け止め、考えているのか。世代限定の投書特集も毎月1回掲載します。
◆連載第1回 (2013.4.13) 同僚の助言に救われ
教師たちの悩みを、退職した元教師がともに考える「教師駆け込み寺」の初の例会を開いたのは、2004年の9月のことだった。
大阪府立高校で00年3月まで国語科教員を続け、関西大学などで教職の授業を担当するようになったが、その卒業生が教職に就き始めていた。電話やメールで「元気にやってるか」と連絡を取ると、「時間に追われ、とにかく大変です。」と悲鳴が聞こえてくる。
大きな行事などがあると、午後9時、10時まで準備することもざら。給食は5分で済ませ、家庭との連絡帳に書きこむ。職員室に座る時間もない。そんな中で、若い教師は、どう子どもを見ていけばよいか分からない。
子供同士のトラブルや保護者からのクレームがあれば、精神的にも追い詰められる。夏休みもない。土日出勤もまれではない。学校5日制以来、忙しさに拍車がかかった。
せっかく教壇に立てたのに、倒れられたら大変だ。そんな気持ちで、知人に呼びかけ、初例会にこぎつけたのだった。
大阪市内の会場に着くと、開始30分以上前だというのに、人が集まっている。奈良、和歌山からも来られている。
父親の車で来られた若い男の先生は既に休職中。教員採用の少ない時期に難関を突破された。顔色が悪く、本人の口からは一言も出ない。父親が話し、メモを取っておられた。深刻な状況の参加者を見て、私たちは活動の必要を強く感じた。
翌年2月、休職して9ヶ月という比較的短期間で復帰された小学校の先生をゲストに、体験を語ってもらった。少人数教育の教科のことが引き金になり、そのうえ子育て、更年期障害もあり、しんどくなった。年配の同僚の助言で受診し、休職し、「適切な助言で今がある」と、話された。
教師同士、横のつながりが難しくなっている中、同僚の助言の有り難さを痛感した、と。その場に、若い小学校の先生が参加しておられた。まだ自分の心情を話すには時間がかかりそうだった。その先生は、ゲストから「あなたの笑顔、すてきですね。」と声をかけられた。「その一言が心にしみました」と、後に私宛のメールに書かれていた。
◆連載第2回 (2013.4.27) 先入観を持たずに
教師間で「黄金の3日間~1週間」と言われる時期が年度始めだ。この最初の3日間、1週間で担任と児童生徒との関係が違ってくるという意味だ。
学級担任は、年度開始n向けてたくさん準備をする。名札・座席表づくり、子供等の氏名の読み方の確認など。そうして、いよいよ児童生徒との対面。初日が肝心だ。担任あいさつは、大きな声で笑顔でと、先輩教師から言われている。できれば、「自己紹介」の入った<学級通信>第1号を発行する。特に初日から3日間でやることがたくさんある。
そのあわただしさの中でも、児童生徒は自分らの担任がどういう人かを、しっかり見ている。仲良くやっていけそうやな、なんか取りつきにくそうやなとか、子供なりに担任像を描く。
新任も入れ、20代から30代前半で教師の7割を締める学校もある。それだけに、「学年」としての共通した取り組みが大事になる。
しかし、教員になるまでに自分の学校体験を除けば、短期間の「教育実習」だけが「教師」としての体験だ。そこで、初めて学校・教師・児童生徒に接することになる。
自分が生徒であった頃、教科の授業や学級の担任について、いろいろ疑問に感じていたこともある。が、いったん教師になると、自分が受けた教育と同じことをしてしまう。特に、いわゆる「優等生」だった人にその傾向が強い。
目の前にいる児童生徒は、じつに多様だ。大きな声を出す子、忘れ物をよくする子、教師の出方を試す子、甘える子……など。自分の思い描いていた「児童生徒像」と大きく違うことだってある。「自分の生徒像」にとらわれ過ぎると、多様な子供の姿が目に入らず、教師の思いこみで動き、子らと溝ができることも。「黄金」が「鉛」に変わる時だ。
物言いが強いなど学級の中で力を持った児童と教師が学期始めにぶつかり、それをきっかけに学級全体がかきまわされ、どうにも対応できなくなった、というケースもある。
「なんで生徒は言うことを聞かないのか」ととらえるか、「自分のイメージに合わせて見てはいけない、一人ひとり違って当たり前」と受けとめるかで、大きく違ってくる。
ある若い教師は、教育実習でこんな体験をした。初日、顔をあわせるなり「ウザイなー、おまえ」と突っかかってくる生徒がいた。暗い気持ちで過ごしていた3日目、この生徒が給食の時間に「センセー、みそ汁お代わりいる?」と声をかけてきた。嫌な生徒だと思い、自信をなくしていたが、「生徒を先入観だけで見てはダメだ」と教えられたという。
目の前の子供をよく観察し、それぞれの特徴、背景にあるものにしっかり目を向ける。そうしないと、自分の先入観にさえ気づかない場合もある。
子供たちは、社会の変動をいちばん敏感に感じて変わっていくのだ。
◆連載第3回 (2013.5.11) 「不可能」越えて得られるもの
新年度が始まると、多くの学校が4~5月に「野外活動」「遠足」などの行事を組む。学年や学級がまとまるよい機会となるからだ。日常の子どもらとは違う表情・行動がみられ、学年団・担任としてクラスづくりのステップにすることができる。
つい先日、乙武洋匡原作「だいじょうぶ3組」の映画を見た。手足がない赤尾先生が担任だ。5年3組の子どもらは驚きの表情で先生を迎える。この絵以外にはいくつかポイントになる場面があるが、その大きな1つが遠足をめぐる場面だ。5年生は高尾山に登ることになっていた。が、100キロの車椅子で登ることはまず無理。3組の子どもらは行き先変更を願い出るが、ダメだった。当日、赤尾先生と子どもらが登れる所まで登り、他のクラスが頂上で弁当のとき、3組は途中で昼食をとる。子どもらは、ここまで赤尾先生と一緒に登ってこられたことに満足する。
この場面を見ながら、かつて勤務した新設高校のことを思い出した。I君という足が不自由で、歩行に困難な生徒がいた。ある時、校内球技大会でソフトボールの試合があった。そのI君のいるクラスは何とかI君を試合に出したいと、クラスのリーダー格のT君がバッターボックスに立つように言った。すると、I君は投手の方に向くのでなく、バックネットに向かって立った。彼は、これまで運動ができない子という扱いをされ、一度もバッターボックスに立ったことがなかったのだ。T君はI君の構える位置を手ずから教え、両クラスの生徒は事態の推移を固唾をのんで見守り、試合は進行していった。
そのI君がいる学級も含め、冬の金剛登山が実施されることになった。登山などしたことのないI君を、そのようにして登らせるか。学級のメンバーは考えた末に、I君の体をロープで固定して後ろから支える者、引っ張る者が1つになって、頂上まで進んでいった。登山途中の生徒たちは顔を真っ赤にし、I君も必死の形相で少しずつ前に進んでいった。
I君の初登山をと意気込む、心優しき1期生の奮闘は、卒業後30年以上たっても当時生徒だった人たちの中に生きている。中学校の教師になったM君は「自分の原点がそこにある」と語った。「友情」といった徳目では教えられない、確かな経験となったのだ。
◆連載第4回 (2013.5.25) 地域とともに育む生活
「ぐっすり寝て、しっかり食べて、すっきり出す」
大阪の南部にある小学校を訪ね、校舎に入ろうとして玄関口に書かれている掲示に目がいった。
学校生活を順調に送るには、毎日の規則正しい生活リズムを身につけることが大事だ。掲示はそれを簡潔に表現している。この三つを確実に実行することで子らの体と心を作る。
数年前、私が大学の教職課程で出会った学生が、卒業後小学校に赴任してすぐ、1年生を担任した。しばらくして会うと、「先生、1年生は上半身より下の問題がまず大変ですよ」と言う。「どういうこと?」と聞く私に、「おもらしする子が……」と。
ある子の足下が水たまりになっている。すぐに保健室に行き、パンツを替える。他に、うんちをした子もいた。その子は兄弟にもまれているのでしっかりしていて、自分で洗って「パンツ貸して」と言う。始めは「えらいこっちゃ」とあわてて処理したり、家庭に一報を入れたり。家庭も新しいパンツを返してきたり……。
が、それだけではない。「私に抱っこしてほしい子がいるんです」と言う。特にプールの時は大変で、次から次へと抱っこしていくことになった。でも、そうしたことで子らと担任とが良い関係を築け、数年後に高学年でまた担任した時、無事卒業までもっていけたと聞いた。
かつてはピカピカの1年生が担任の顔をみつめ、何を先生が言うのかと見守る姿があった。そんな頃、子どもたちに「抱っこの宿題」を出した福岡県の女の先生がおられた。「家に帰ったらおうちの人に抱っこしてもらってきてね」と。次の日、抱っこしてもらえなかった子がいたが、先生は一人ひとり前に並べてぎゅうっと抱きしめたという。
スキンシップも大事なのだが、晩9時から10時までに寝かせているか、朝食は取らせているか、直食のあと便所に行く習慣をつけているか、こういうことでだいたい規則正しい生活ができるかどうかが決まる。
学校生活の基礎となる生活リズムを養うには、家庭の力が不可欠。昔は、家庭・地域が学校に関心を抱く、いつでも学校のためにひと肌脱ぐ、そうした関係ができていた。それが希薄になっている現在、意識して地域性を回復していく努力が必要になる。それに逆行する「小学校の選択制」など、とんでもない。
◆連載第5回 (2013.6.8) 家でしか見えない顔
年度始めの始業式から2ヶ月が過ぎた。学級のカラーもできつつあるだろう。担任として名前と顔を全部覚えたところで、家庭訪問週間を迎える。
長く小学校教師をした後、大学に移った園田雅春さんと会って、近刊の「自尊感情を高める学級づくりと授業」という本を頂いた。手に取るや夢中に読んでいった。そこに教育評論家の故・遠藤豊吉さんが、小学校教師時代に家庭訪問した時のことが紹介されている。
「きょうは、家庭でのお子さんの素敵な姿を三つ聞かせてください、と私は行った先々で、必ずそう言うんですよ。これを聴くのがとても楽しみでね……。どの親もいい顔をして語ってくれますよ。担任がまったく知らないことをね」
玄関先で3分の立ち話といった家庭訪問では、「我が子のステキな姿」の離しも出てこないだろう。が、園田さんから“黒いランドセル”という話を聞いた。小学校に入学してきた女の子が黒いランドセルで登校してくる。「あいつ、女やのに黒いのを……」と、揶揄する他の子の声が聞こえてくる。それが毎日繰り返される中で、いたたまれず転校していかざるをえなかった女の子。
この子の2歳年上のお兄ちゃんが小児がんで亡くなったという。それで、この子は……。家庭訪問をして初めてわかる事実。からかわれたこの子の気持ちなど誰ひとりわからないまま、転校していったのだ。
当時、男の子は黒、女の子は赤が「社会通念」だった。それをそのまま受け入れてしまっている人権感覚のなさ。それは大人が身につけたものだ。
ずいぶん前に担任した男子生徒のことを思い出した。目立たないおとなしい生徒といった印象だった。が、家に行くと、その生徒を筆頭に小さな子が5人もいる。この生徒は、アルコール依存症の父親が働いている姿を見たことがない。母親が二つの仕事をかけもちして生活を支えていた。生徒が長男で、一家の柱だ。兄弟の面倒もよく見ていた。こうした状況で荒れもしなかったのは、非常に芯が強かったのだろう。
高校卒で就職した企業に今も勤めている。既に35年になるはずだ。同じ地域で一緒だった卒業生が集まる場にも、顔を出していた。案外よくしゃべる彼にほっとしたこともある。卒業後まもなく、父は亡くなり、母は出て行った。下の兄弟は結婚し、子どもがいる。彼は今も独身だという。この人の深い沈黙を聴き取れなかった悔いが残る。
◆連載第6回 (2013.6.22) 読み続けているもの
高校教諭の頃、卒業を前にした生徒の母親が学校を訪ねてきた。大阪から離れた大学に入るため、娘の下宿探しについていった。住む場所が決まったとき、その生徒は、母親に「後のことは私一人でするから、もう帰っていいよ」と言ったらしい。そこまで言って母親が泣き出した。この卒業生は、授業料から生活費から、すべて自分の働きと奨学金で賄うと言って、それを実行した。遠方に出すだけでも心配なのに……親の世話にならないという我が子に不安が募ったに違いない。
母親が「情けなくて……」と言いながら、取り出したのが古ぼけたノートだった。母親は娘が小さい頃から公共図書館に連れて行き、借りて読んだ本の題名をぎっしり書きこんでいた。「お母さん、これだけたくさん本を読んで育った、娘さんの立派な成長と自立の記録ですね」。そういう私に、母親はようやく笑顔になった。この生徒は、福祉大学を卒業した後、NPOに属し、独り立ちした。
「10分読書」とも呼ばれ、今や全国で広がりを見せて実践されている「朝読(あさどく)」のすすめを論じて、心理学者の河合隼雄が「子ども自らが読む本を選べるのもいい。10分間という枠だけを与え、そのなかで子どもは自由や自主性を体験するのだ」「自らの力で獲得したものは長く残り、その人の人格形成に大いに役立つのである」と語っている。
この朝読が行われ始まるずっと以前、私が国語科の授業を担当していた頃、折りに触れて本の紹介をしていた。その後、府立高校の校長になった卒業生から、「僕は先生に読書ノートを作ろうと言われて、ずっと実行してたんですよ」と言われた。見せてもらうと、高校の欄には青春時代を扱った「車輪の下」「友情」や「破戒」、大江健三郎の「ヒロシマ・ノート」もあった。読んだ日付、書名、短い要約と感想が記録されていた。それは大学生、教員になった後も続けられた。そして、彼はバスケットボール部の顧問として、部員に読書を含む多くの課題を与え実行させていた。
彼が顧問として接した部員の一人は、「顧問は私が嫌がる事ばかり強要した。定期テストで70点以下は練習させない、長期休みに文庫本を1冊読み感想を提出、午前の練習のあと自主勉強、……そのお蔭で嫌だった本が今では読まないと眠れない」と書いている。
多様な可能性を培うスポーツ精神を実行してきた顧問の面目躍如ぶりを語っている。
◆連載第7回 (2013.7.13) 地域一体で「小中一貫」
子どもたちの元気のいい声が響いている。「abc…」と、外国からきた英語指導助手の先生が声に出した後、大阪府吹田市立竹見中学校の英語の先生が説明を加えながら発音し、生徒が続く。中学ならどこでも見られる光景だ。が、この教室で大きな声を出しているのは、同市立桃山台小、千里たるみ小の6年生の児童たちだ。
この小学校2校、中学校1校は、それぞれの既存私設を利用しているが、「千里みらい夢学園」として、2011年から小中一貫教育に取り組んでいる。週に1度の「金曜日登校」で、両小学校の児童が中学校にやって来る。中学校の先生が教える英語その他の時間やそれぞれの小学校の先生の授業もある。
また、授業後は「みらい夢タイム」が設けられている。この日は、両小学校の子どもたちが合同チームを組んでバスケットボールの大会。立てた計画によっていろんなゲームを中学生と楽しむ交流の場。次の週は、中学の部活に参加し、中学生の部員から新設に指導を受ける。
小学校から中学校への進学で「中1ギャップ」という問題が起こることがある。人間関係や学習難易度の急激な変化によって、新たな中学生活になじめず、いじめや不登校などの問題が発生する場合があるのだ。
同市では、中学校区をつくる2小1中で交流を深めることで問題の解消に努めてきた。千里みらい夢学園になるまでは、1小1中の小中連携から始まり、少子化の波で中学まで単学級になったのを是正するために校区を変更、2小1中で現在の形になった。先生方は、その中身作りにまい進している。
一つは教科のカリキュラム(9年間)の一貫性、小中共通の授業づくり。加えて、小・中学校以後さらに広がる生徒の世界でコミュニケーション力をどうつけていくか。これが共通の目標であり、それに沿って取り組む。
二つの小学校の先生が互いの授業を見る。中学の授業・教科書を知って、小学校からの発展を児童に伝えることもある。こうして、教師間の交流も金曜日を軸に少しずつ進んでいく。これは中学の教師にとっても大いに刺激となる。
一方、小学校6年の教師の手で金曜日登校の中身が「前へ」という学年通信で他学年の先生に伝えられる。こうして、小中の先生同士が地域であいさつを交わし、子どものことを話せる関係ができてくることで、小中一貫の実が徐々に上がっていく。
◆連載第8回 (2013.7.27) 就学前に育むべきは
大阪府枚方市の市立小学校と、隣接する幼稚園の両方におじゃました。2限と3限の間の20分休憩、昼休みには、小学生との「交流」遊びが行われていた。ボール投げ、砂場での遊び一つとっても、年長の小学生と園児が場を共にする。いわば昔から見られた、異年齢の「子ども集団」ができているのだ。
午後2時前後には、園児の保護者たちが三々五々わが子を迎えに来る。が、わが子を見つけてすぐ帰るのではなく、教室の前に園児は座り、担任が保護者向けに必要事項を白板に書き、周囲に集まった保護者に説明している。このような「終礼」が市全体の方針でされている。横浜から転勤族でやってきた保護者は、「三つ目でやっといい幼稚園に巡り合いました」と、笑顔で話す。
この担任と保護者の毎日の「出会い」が、小学校では「連絡帳」になる。気になる園児をめぐっては、終礼のあと保護者が残り、担任と話すこともある。それだけで解決しないと、園長も入り教職員にも諮られる。少子化の波が押し寄せ、私立と公立との園児の「争奪」は激しいと聞くが、大切なのは保育を担う幼稚園と家庭との連携である。
ほぼ10年ごとに改定される「学習指導要領」で、1998~99年から「生きる力」の育成のため、学習内容の削減、総合的な学習の時間の新設、中学の選択教科の拡充が盛り込まれた。それが10年後の改定で、「ゆとり教育が学力の低下を招いた」とする声に押されて、文部科学省は教科学習の時間を増加、小学校での外国語活動を導入し、中学の選択教科を廃止した。
その影響か「音楽や芸術の活動をするよりも、もっと勉強してほしい」という親が、3月のベネッセ教育総合研究所の調査では40%、4年前の調査より8%増。「子供と美術館にいくことがほとんどない」親が78%だったという。そこで、「美術離れを食い止めたい」と出前授業に力をいれる大学が出てきている。
こうして見てくると、小学校に入る前までに「文字や数字」に触れさせ教科の授業を重視する保護者が、「絵本」の読みきかせ、子らのすてきな発想を書きとめるなどの大切さに、どれくらい目を向けているかが心配だ。
幼少「交流」を盛んにし、幼稚園とは違う「学習」中心となる小学校にスムーズに入っていける素地を、親や教師が一緒になって培っていくことに、関心をもってほしい。
◆連載第9回 (2013.8.10) 「荒れ」と向きあう
何人かの児童生徒が、教師に罵声を浴びせたり、暴力を振るったり、教室に入らなかったりといった状態が日常であった。学校の規律が子らの中に通らない「荒れ」が蔓延していた。子どもを追っかける教師は、疲労困憊する。その場から逃げたくなる。
こんな時、学校はどうするか。かつて宝塚の中学校を立て直した校長がいた。赴任した先の校長室は、すでに生徒によって占拠(?)されていた。校長は「お前たち、何をしているのか。ここはワシの仕事をするところじゃ。出ていけ!」とは言わなかった。静かに「ここをちょっと空けてくれるかな。この白板に書きたいんやけど……」と生徒に場所を空けさせる。
その後、生徒の下足室の掃除を始める。どろどろになった靴箱がよみがえる。次は、校庭の掃除をする。先生方には必要な指示をした後、出張に出かける。しばらくすると、荒くれていた生徒が、校舎から「行ってらっしゃい」と、手を振って見送るまでに。
一方、堺市の小学校の校長はどうしたか。これまでの長年の経験から、先生方を前に、「子どもらに詩を書いてもらおう」と呼びかける。出てきた作品は学級通信などで紹介し、さらに、その中から堺市の児童文芸誌「はとぶえ」に載せよう、そう言って先生方を励ました。
その「荒れ」の最中、4年生を担任していた若い先生が、その提起を受け発行した通信に、こんな詩が載っている。
-天にいるお父さん/だいすきだった分/わたしはたくさんたくさん/生きるからね/だからまだ/お母さんを天には/つれていかないでね/もし行ってしまったらわたしは/ひとりぼっちになっちゃうからね/以下略(M)
-空を見てると とってもいい気持ち/ぼーと見てると 頭がからっぽになる/(略)空を見るのは大好きだ/ひとりで見るのもいいけど/みんなで見ると もっと楽しめる(Y)
自分の詩が「はとぶえ」に載ることを期待する子ら。「空をみんなで見る」ことを願う子。兵庫県が生んだ教育の先輩・東井義雄は「青少年の荒れは残酷な人間評価に対する反乱である」と記す。上から「テストの点を上げろ」と叫んでいると、点数に表れてこない子らは「反乱」するしかない。先の小学校では、校長の呼びかけに応えて、詩から作文、新聞づくりへと進め、学力がぐんぐん伸びる学校に変貌していったという。なにより子らの自尊感情が高まったことがカギだった。
◆連載第10回 (2013.8.24) その時、何ができるか
東日本大震災から2年5ヶ月がたった。復旧とはほど遠い現状で、「震災の記憶」とどう向き合い、それを記録していくか。その作業を通して厳しい現実をどう歩み続けるか。18年たった阪神大震災当時を思い起こしながら、宮城県女川の地を再訪した。
この中学校を訪問しようと思いたったのは、『みあげれば/がれきの上に/こいのぼり』という本に出会ったからだ。国語科の佐藤敏郎先生が震災から3ヶ月後の授業で「今の素直な気持ちを五七五で表してみよう」と働きかけ、できた歌を遠い宇宙に届けたという。
阪神大震災の折、私の古里・神戸から梅田に出ると、震災などなかったかのような現実を前にして、何か被災地に向けて届けられないかと考えた。友人を救助するのにスクーターを高槻(大阪府)から走らせた生徒がいた。避難してきた転校生もわずかにいた。今この時期にやっておかなくてはと、「被災地の各方面の人に手紙を書こう。各自のテーマで大震災の新聞記事を切り抜き、コメントをつけよう」と呼びかけ、教室中を新聞紙だらけにし、慣れぬ手で高校生は懸命に手紙を書いていった。『阪神大震災を心に刻みつける』という題の冊子にまとめ、要請に応じて各方面に送った。
女川の中学生の先の本の題になった俳句に、交流のあった各地の中学生が句を重ね、さらには世界各国の人が「おもい」を表現して送ってくれた「文」を七七にする作業が同じ中学生の手で進められる。
みあげれば がれきの上に こいのぼり
あきらめないと空を泳いだ(パキスタン)
生きている限り幸せはある(ブルンジ)
国内の中学生の重ねた思いは……
戻ってこい秋刀魚の背中にのってこい(女川)
大切なもの全部かかえて(共立女子)
震災にいつもの幸せ教えられ(女川)
折れた心をみんなでつなぐ(亀岡中)
これまで佐藤先生は、5月、11月と繰り返し、この5月で5回、表現の場を設定した。
これと同じような取り組みを、兵庫県神戸工業高校(定時制)の生徒たちに働きかけてきた国語科の南悟先生。生徒の労働や震災をめぐる厳しい現実を短歌表現にと促し、すでに3冊の本(『生きていくための短歌』他)になっていることを佐藤先生に伝えた。
学校の日常性を破る出来事に遭遇した時、教師に何ができるか、その一端をこれから取り組みは示している。
◆連載第11回 (2013.9.14) 住民とともに生き抜く学校
少子化と過疎化が学校の児童生徒の減少を加速している。
山口県岩国市に編入された錦町宇佐郷にある向峠集落に出かけた。三つの山と清流に囲まれたその地区にある宇佐川小学校は、私が行った当時、児童11人のミニサイズ。山村留学で2人ほど増えると聞いた。
校庭に来る鳥のさえずりに耳を傾け、望遠鏡をのぞき込み、観察する。また、川にすむオオサンショウウオの観察の場を地区の人が提供し、観察研究の成果を市と県で発表し、最優秀賞に輝
いたと聞く。運動会ともなると、住民総出でにぎわい、種目ごとに歓声が上がった。住民らは過疎のなかに、わずかに存続している学校や新たに発足した通信制高校をもり立てていこうと、協力を惜しまない。宇佐川小学校を訪ねた折も、学校の行事や教育活動に全面的に力を貸してくださる様子がDVDになっていた。
同じく山口県上関町の離島・祝島の小学校の児童は4人。早朝からマラソンの練習に励んでいた。海沿いの道路のあちこちに年寄りが座り、手をたたいて応援している。みんな笑顔だ。校長と、私が教えていた学校の卒業生を含め計3人の先生方で学校を運営している。「この島全体が総合学習の場です」と、卒業生は言う。養豚場ができ、船大工がいて、ビワの生産が盛んだ。映画『祝の島』(纐纈
あや監督)の舞台として知られ、4年に1度、神楽奉納の一大行事が厳粛に執り行われている。
都会でも少子化で、各学年1クラスの小学校もある。少ない教職員がフル回転しなければ運動会一つ運営できない。先生方はてんてこまいだ。大阪市内の小学校の運動会を半日見せていただき、それを痛感した。しかし、そのかいあって、児童らのはつらつとした表情が見てとれた。「この学校は3世代が通っており、地域の熱いまなざしに支えられています」と、校長は満足げに語られた。PTAの役員さんも、朝早くから協力していた。
現在、多くの学校で、学校や教員にクレームをつける保護者がいる。が、個々の教員だけでなく、学校全体の動き、過酷とも言える教育条件・管理強化の中にあって懸命に取り組んでいる教員全体の動きをもっと知って、もり立てていってほしい。そのために「学校だより」「学級通信」「学校ホームページ」などにも目を通してほしい。学校が請け負わなければならない教育課題が増え続ける中だけに、その願いは切実だ。
◆連載第12回 (2013.9.28) 「勇気の分数」の効果
敗戦後のベビーブームと言われた頃に生まれた子らが高校に押し寄せた時期、1960年代半ばのことだ。その頃、私は信任教師としてある私立高に赴任した。
過疎化や少子化とは正反対の、1学年57人クラスを新任教師らも担任した。生徒は朝出席を取った時は、確かにいた。が、外から「引きとりに来てほしい」という電話が入る。万引きその他、さまざまな問題を起こしていた。
今日の深刻な薬物乱用やネットいじめなどとは違い、まだ行為は単純だった。が、それでも「退学」という処分が職員会議に上る。学校に残して「見守る」という指導ができるはずなのにと思っても、新任もベテランも発言しない、できない雰囲気だった。
「生徒を守る」ためには、まずは担任が学年などの教師と横につながることが必要だ。そうした問題意識が教師の中に芽生えていき、当時の私学にしては珍しく「組合結成」に職員が動いた。すると、これまで自分の担任クラスの生徒が退学処分になってもものが言えなかった担任が、職員会議で発言し出した。それも、後に続いて発言してくれる教師の存在が確信できれば、のことだ。
事実、新任担任であれ、経験者であれ、勇気をもって発言する人が次々と現れ、それに連れて生徒会も活発に動き出した。全校観劇の後、生徒から出された「感想」を、全校放送で流すといった学校始まって以来の出来事も生徒の動きを助長したのだろう。来週の学級活動(ロングホームルーム)にどういう議題を掲げるかを、放課後に有志の生徒が残って話し合うことが私のクラスではずっと続いていった。
長年小学校で教員をされ、大阪教育大学に移られた園田雅春さんが、「勇気の分数」ということが担任した子どもの間で生まれたと言っている。「いじめNO!」と言うには、1人では難しい。1人の子どもが言う場合、その後に1人でも続いてくれたら「2分の1の勇気」、2人が続いてくれたら「3分の1の勇気」でいいと。
そういった行動が子どもたちの中から生まれるには、常日ごろからの「学級内の仲間づくり」が必要だ。休み時間に「いじめ」は発生しやすい。とすれば、休み時間に班活動や係活動で子どもらが協力することを促す。グループ化しやすい子ども世界の外に学級の「協働」の場面を作り続けることだ、と私は考える。
教師より先をゆく子どもらの姿にまなび、励まされる、共に「自尊感情」を助長する営みは、半世紀前より今の学校現場の方がより切実だ。それには、教師の肉声が子どもらに発信される必要があるのだが。
◆連載第13回 (2013.10.12) 「つながり」をひろげる
子どもらと毎日接している担任には、学級の中に気になる児童生徒が必ずいる。一人親家庭の子ども、両親がそろっていても単身赴任家庭や親が失業した子ども……そうした中で子育てに不安を覚える親。これらのことから起こる育児放棄や親の虐待なども気をつけなければならない。
そうした子らが抱える問題を自らの教育課題として取り組む場合、一人でことに当たっている担任が多いように感じる。隣の同僚・管理職に事情を「報告」し、同じ学年の担任相互に「連絡」し、関係する教員間で「相談」する。この「報・連・相」を怠れば、問題をより複雑にし、解決を遅らせることになる。
また、気になる児童や生徒にばかり目がいくため、目立たない子らに声かけしていないことも多い。時に自分が担当する児童を客観的に見ることができる場面が必要になる。
先日訪問した京都府下の小学校で、地元のプロサッカーチーム「京都サンガ」が講師を派遣する「サンガつながり隊」の出前授業が行われた。午前は5年生、午後は6年生。指導に当たるコーチを中心に運動場で掛け合いしながら、ゲーム感覚で子どもらは動く。初めは、2人がペアになり、向かい合って靴先をくっつけ、右手を取り合い、どちらかが相手に体を動かされたら他のメンバーと交代し、それを繰り返す。
こんなふうに児童同士が「つながり」をつくる行動が次々と進んでいく。その時、体操着に着替えずに「見学」していた児童が運動場の輪に入ってきた。校長が特例として参加を認めたのだ。
さまざまなゲームが進む中、ボールを蹴りながら三角標識を回ってきたグループが次々と人数を増やしていく。2の倍数で、4,8,16………と輪が広がり、最後には全員が一つの輪に。その過程で、途中参加の体の大きい男子が自ら声をかけリーダー役を買って出ている。もし、ここで、あのグループと手をつなぎたくないと誰かがささやき、それが広がれば、このゲームは成り立たなくなる。
「人とつながる」ことを心身を通してつかむ活動を教師が日々心していかないと、ちょとしたことで協力関係が崩れていく。「いじめ」も、そういうところから始まっていく。外部後からも借りながら、日々教師としてやっていくべきことを担任らはその日の「振り返り」の場で確認していた。
◆連載第14回 (2013.10.26) 原点を思い出す時
自分が教師を目指した時、何を考え、志していたかを思い返すことが時に必要だ。
教育実習生の受け入れは、現場教員にとって「重荷」である。仕事に追われる教員にとって、余分な仕事を引き受けさせられるという感覚がぬぐえない。が、これから教師を目指すという実習生や新任教員を通して自分の日々の教育活動を振り返る何よりの機会であると受け取れる人はさいわいだ。
長年大学で「教育実習」科目を担当し、学生の実習中も含め学校訪問を続けて来た。その中には忘れられない人がいる。
中学で実習した千里さんは、不登校の生徒に目がいく。自分も生徒であった頃、激しい葛藤の中でもがき苦しんだ。集団に属している人たちからの物言わぬ圧迫が、そこからはぐれてしまった者にとってどんなに恐怖か。教師から見たら「いい子」と見える子でも、自分をすり減らしつづけて物が考えられなくなる子がいるのだ、と。その体験から、4分の1程度しか出席できない女生徒に何度も手紙を書く。
他方、純子さんは仕事をしながら夜間大学に通い、定時制高校で実習させてもらった。先生方は荒れる生徒の対応に追われ、実習生の存在に目がいかない。先生方に挨拶したのに、誰も返してくれない。「週4日、夕方に仕事を終え、家とは反対の方向の電車に乗って大学に向かっていると、ふと(私はなぜこんなことをしているのだろう)と教職を取ろうと決めた初心を見失いそうになる時がある。そんな時は、大学の教育実習の授業で配られたプリントを読み返したり、あのつらかったはずの実習で自分の心が震えた場面を思い出してみたりする。そして、人間の心を相手にする仕事だから大変でしんどいけれど、心と心がぶつかって感動や喜びで震える体験ができるのもこの仕事だから……」と、教師の仕事に魅力を感じた体験を思い返す。
別の学生幸地さんは、故郷沖縄で教師になるという夢を抱き、「へき地教育に身を捧げたい」と願う。たとえへき地でも管理教育は免れないだろうが、子どもを支えてきた家族、地域社会、自然、それらが崩壊せずにある郷里が教育の原点だと。首里高校に入る夢を果たせなかった彼の父のことを心に刻み、郷里で教師を目指すと語ってくれた。
困難な時こそ、初心・原点に返る時なのだ。
◆連載第15回 (2013.11.09) 教え子がつなぐ新美南吉
作家新美南吉の「生誕百年」の行事が、郷里の愛知県半田市や安城市を中心に繰り広げられた。わずか29歳でなくなった南吉が今も多くの人に読まれているのは、小学4年のすべての国語教科書に『ごん狐』が掲載され、推定6000万人の子どもが読んだということが大きい。
南吉は1938年から5年間、安城高等女学校(現愛知県立安城高校)に勤務した。最初に担任した、現在87歳になる教え子で、なお健在の方々によって「南吉先生」が語られてきたことも、長く読み継がれてきた理由として大きい。その教え子の一人、加藤(旧姓山口)千津子さんを安城のご自宅にお訪ねした。加藤さんはじめ54人の生徒に、南吉は英語と国語を教えた。作文の時間を設け、「見たまま感じたままに書く」作文を奨励した。提出されたノートや日記に全部目を通し、短文で批評を書き、自主的に書かれた「詩」に自身の詩も加え、わら半紙に印刷して第6集まで「詩集」を発行した。南吉は続けて発行を企画したが、太平洋戦争の戦況悪化で紙の配給がなくなり、断念したという。
卒業生は南吉の死後生家を訪ね、父親から、克明につけられた「日記・ノート」を借り受け、手分けして活字に起こし、今は全集にも入っている。その解読と清書を、加藤さんらが中心に担ったとお聞きした。日々の南吉先生とのやりとり、またノートの日録を振り返り、加藤さんは「先生は正しい日本語を使っておられました」と繰り返された。
花や動物が好きだった南吉が天気の良い日は戸外に生徒を連れだし、自分の感性でとらえた詩的表現を「言葉のシャワー」のように、生徒たちに降り注いだという。関連して加藤さんが記憶しているのは、卒業に際し生徒らが「色紙」に一筆お願いする場面で、一味違った「詩的表現」で1行添えて渡したという。
実際に南吉の育った故郷を歩き、作品の舞台を肌で感じたり、また『ごん狐』に限らず『手袋を買いに』『おじいさんのランプ』、さらには優れた詩篇の数々に触れたりすることで、今の先生たちも宮沢賢治に並び称せられる南吉ワールドに児童生徒を引き込み、子らの感性の畑を耕し、思索を鍛えていくことができる。
今日の困難な教育条件下にあってなお、何道と教え子さんらの関係と同様に、先生方が連綿と続ける取り組みが子らの成長した後にも刻み込まれていることを、私は確信している。