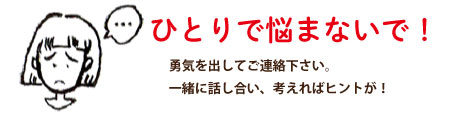お問い合わせをお待ちしております
TEL. 00-0000-0000
営業時間 AM10:00 ~ PM20:00
コラム コロナ禍に想う
◆ひとは何によつて生きていけるか?
~戦争下・コロナ禍の暮らしを生き抜く知恵とは
戦争下にあって、まずは「食料」が底をついていく人々の暮らしは、想像するだに恐ろしい。ウクライナの地下に開じ込められた子ども・市民・兵士はそういう事態に陥っているのだ。
これは、あの第二次世界大戦に発展したもとにある日中戦争。日米戦争によって日本社会でも長く味わわされた苦悩する姿に重なる。とりわけ、末期の1945年の沖縄の地上戦で味わわされた沖縄住民の苦悩にもつうじる事態として私には感じられる。ガマが暮らし、医療の現場となり、銃弾が飛び交う中を、ひめゆり学徒隊メンバーは、行き来したのだと。負傷兵士の手当から食糧確保まで、まだ10代だった彼女たちが味わった恐怖の体験。それは《ひめゆり記念館》を見学することで、わずかに追体験できる。
その追体験をとおして私たちは、わずかであっても今ウクライナ(とりわけ南東部の地域の)市民の恐怖と飢えとに苦しむ人たちのことを想像することができるかもしれない。
毎日新間の5月25日には、そういう問題提起として《戦争と芸術》をオピニオン欄で取り上げた。
その「論点」のリード文には、次のようにその主旨が書かれている。
一ロシアのウクライナ侵攻を受けて、ロシアの芸術家たちが欧米の劇場や芸術祭などから排斥される動きが続いている。一方、ウクライナでは多くの芸術家が国を去ったり、ロシアとの戦闘に身を投じたりしている。
戦争に対して芸術は何ができるのか、そして芸術家は戦争にどう向き合うべきなのか一
この「論点」では、いつものように3人の論者の寄稿と聞き取りで構成している。以下に、その寄稿文と聞き取りの内容を要約的にとりだし、考える材料としたい。
●
◎大野 和士。新国立劇場オペラ芸術監督
==私と東京都交響楽団は4月、東京芸術劇場で行われたコンサートでプログラムに載っていない、ウクライナ人の現存する作曲家の作品を特別に添えた。/ それは、シルベストロフ作曲「ウクライナヘの祈り」。若い頃はアバンギャルドの旗手として知られていた彼だが、今回の作品は、2014のロシアによるクリミア侵攻で犠牲になった人たちのために書かれた。ウクライナの民謡に基づいた分かりやすく、情感のこもった作品であった。この曲は本来合唱曲として書かれたが、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、オーケストラの編曲版ができて、世界中の演奏家が取り上げるようになった。演奏を聴いた聴衆からは、切なさを湛えた旋律に、啜り泣きの声が聞こえてきた。/最近日本では、ロシアの音楽や文化を避けようとする機運が少なからずあるのを感じるが、それは狭量のそしりを免れないだろう。この「狭量」という言葉は、「他人を理解しない」ということとある意味で同義語であって、文化英術とは対義語のような関係にある。そのことを証明するために音楽文化の歴史上の現象とも呼ぶべき二つの出来事を挙げたい。
*1941年から45年まで、ナチス政権の下、チェコのユダヤ人はテレジン収容所に一番多い年で5万8900人ほど収容された。それは「片道切符」と呼ばれ、そこでいったん収容されたのち、終着駅(アウシュビッツ)に送られていった。しかし、そのテレジン収容所では、多くの音楽家たちが収容された人びとを鼓舞し、ひっそりと隣の学校からピアノを運んだりして、リハーサルを重ねていた。とうとう、チェコオペラの聖地ともいうべき、スメタナの「売られた花嫁」の全曲演奏を成し遂げたり、名指揮者で同じく収容所暮らしだったカレル・アンチェルの下、小さなオーケストラの演奏会も行われたりした。聴衆は、過酷な労働と食事、住居環境に耐えながら、演奏会の時だけ、時がたつのも忘れていたという、それが、自分が人間としての証を感じる唯一の機会だったからである。
*第二次世界大戦が終って、まだ劇場やコンサートホールの再建も進まない中、英国の作曲家、ブリテンは「戦争レクエイム」を作曲した。その歌詞は。第一次世界大戦に従事し弱冠25歳で亡くなった英国の詩人、オーエンの激烈な反戦詩と、ラテン語のレクイエムの典礼文を、ブリテンが組みあわせてできあがった。そして3人のソリストには、英国人のテノール、ドイツ人のバリトン、ロシア人のソプラノを配し、男性2人には敵である兵±2人を、天使の役割を担った児童合唱団に囲まれた女性歌手にはラテン語のパートを歌わせた。殺伐とした兵士の歌が、やがて天へ召される仲間として昇華するという音楽を作り上げた。
この曲の目的は明らかである。初演の1年前のみ1年に、いわゆる「壁」の建設によって、戦後間もなく再び深く分断された現実世界とは反対に、言葉の力で、かつての敵国に永遠の融和をもたらすことであった==
○
音楽は国境を越え、民族をこえ、ひとびとを共感の輪につなぎ、「生きる」勇気を与えることを、大野氏はこの寄稿によって訴えたかったのだ。どんな困難な状況下にあっても、音楽の力で結び合わされ、生きる勇気を与えられるのだ。この大野氏の寄稿された文章を読み、そこで紹介されたエピソードを知ることで、何より私自身が目に涙を湛えながら、身体の奥深くから湧き上がってくる感情の発露をもとめ、なにかせずにはおれない気持ちになるのだ。
も'一つの寄稿は、キュレーター・美術評論家の飯日高讐さんのもの。見出しは《人間の「総体」示すことに役割》。どういうことだろうか、やはり書き写してみよう。
==・・グローバリゼーションの過程で真の政治なるものが終焉し、政治の不在状況に陥っている。軍事衛星やコンピューターテクノロジーによるシミュレーションを駆使した戦争へと突入し、あたかもリアルタイムの黙示録を迎えているかのようだ。このような不条理で差し迫った状況に、芸術が存在する理由や役割とはいったい何だろうか。/これまで、多種多様な宗教や政治的イデオロギーが「愛と平和」を説きながら、自らと異なる宗教やイデオロギーを排除してきた。聖戦の御旗を掲げ、いわゆる「神々の戦争」「ヘグモニー(覇権)の闘争」として戦争やテロリズムを繰り返してきた。
しかし、「戦争と平和」というテーマで議論するとき、宗教や政治、民族といった枠組みのみで行うのでは十分でない。一人の人間の精神性や意識が集団化した時、いかに妄想的な現実が生まれ、戦争へと導かれていくのか。そうした人間の内面性が生みだす「戦争状態」をめぐって問題提起していくこと、そしてナチスの残虐行為が全ての人間の「総体」の一部に含まれていることを知った上でなくては、本質的に戦争と向き合うことにならないのではないかと問いかけることが芸術の役割であり、存在理由だろう。
「文明は野蛮の対極にあるものではなく、文明こそ野蛮との親和性を持ちうるものである」。 ドイツの哲学者、アドルノはホルクハイマーとの著書「啓蒙の弁証法」でそう述べている。そのような「文明」が引き起こしたアウシュビッツの悲劇の後で、文明への批判が根本的に為されないまま放置されるのなら、本来の意味の文化である「詩作」ですら、人間の活動から最も離れたところにある野蛮を体現していると言わぎるを得ないのだ。歴史をひもとくことにとどまらず、今ほど「全体主義の起源」を探求する必要性が高まっている時代はないのではないか。
「文明」と「野蛮」を対立する構図で捉えず、多様な方法論と知性を用いて人間に内在する自己矛盾を見事に浮かび上がらせた作家がいる。1日ドイツ出身の画家、ゲルハルト・リヒターだ。6月から東京国立近代美術館で回顧展を控えるこの作家は今年90歳を迎えた。戦前から戦中、戦後に至る時代精神(戦争の記憶)と真正面から対峙してきた。そして作品を通して人間存在そのものを浮かび上がらせ、存在感を放ってきた作家だ。
彼は「秩序」と「混沌」、「生」と「死」、「美」と「醜」、つまり表層と深層をその境界で区別することをせず、理性的な記憶に止まらない身体的な記憶を呼び起こすことによって「文明」と「野蛮」を対峙させているのだ。リヒターの作品は、すべての人間の「総体」を浮かび上がらせる両義的な芸術の存在が今、必要とされていることを示唆している==
飯田氏はやや難解な用語をつかって戦争と芸術の関係を論じている。が、けっして架空のことを言っているのではない。私が下線を引いた個所にしっかり目を留めたい。「人間に内在する自己矛盾」「人間存在そのものを浮かび上がらせ」るその作家活動、作品を「回顧展」を通して何としても自分自身確かめたいと強く思う。
これまで私は「人間存在」という言葉をよく使ってきた。その存在は、一筋縄で捕捉することができない「矛盾した存在」「その矛盾から目をそらせず、矛盾・混沌をうけとめ、ごまかさず生きつつある存在」であると、とらえてきた。
現実政治の世界で、いかに優勢。有力であろうと、いったんことあれば一日散に逃げだし、かつて自分たちが語っていた「言葉」「政治上の立場」をなげすてる人間がどれだけ多いことか。 ヒトラー、スターリンなどという「極悪人」と日される人間と自分は同じ人間なんだという自己認識なしに、困難にたちむかうことなどできない。その日暮らしの一市井のひとならいざ知らず、いま世間の脚光をあびている人間がいざ窮地に立てば、すたこらサッサと身をかわしていく無様さは、これまでも何度か目撃してきたし、これからも現れてくることだろう。
そういう無様さをさらさないためにも、飯田氏が最後に述べている「表層と深層をその境界で区別することをせず、理性的な記憶に止まらない身体的な記憶を呼び起こすことによって。・・」という箇所の「身体的な記憶を呼び起こすこと」というところに、再度目を向け、刻み込みたい。理性=頭、感性=身体・肉体、この後者を私は「本当の自己」として理解したい。そのことを確かめるためにも、6月に催されるグルハルト・リヒター回顧展には、ぜひ足を運びたい。
飯田氏が寄稿文で書いているように、「今ほど《全体主義の起源》を探求する必要性が高まっている時代はないのではないか」と。偏狭なナショナリズムだけが問題であるはずがない。
○
「論点」のもう一人の論者は、彫刻家・評論家の小田原のどか氏だ。見出しは「政治性と無縁の作品はない」だ。やはり必要と思われる個所を引用しながら、考察を進めたい。
==日本美術史で、戦時中は「彫刻の空白期」とされてきた。戦意高揚のため作られた多数の彫像は「芸術的価値が低い」とされてきた。この評価は「政治や戦争と芸術を切り離したい」という欲望の表れだろう。(しかし)実際には、作品の背景に必ず時代の必然性や制約がある。そこに着目する必要があるだろう。
たとえば、彫刻家の北村西望は戦前、東京。三宅坂の「寺内元帥騎馬像(寺内正毅)」など多数の軍人像を作り、戦後は長崎市の平和祈念像などを作った。同様に戦前戦中は軍国主義、戦後は平和の像などを作った人は多い。彼らは戦意高揚彫刻を「単に依頼があったから」、あるいは「材料確保のため」、さらには「仕方なく」作ったと思ってきた。(このように)そもそも、日本に近代美術は、誕生時点から帝国主義との結びつきが強かった。芸術家に自立した個人として社会に疑間を持つ姿勢が育ちにくかった。
戦後の1951年、寺内元帥像のあった場所に、電通が「平和の群像」(正式名は広告人顕頌碑)という女性像を建てた。日本の公共空間に誕生した最初期の女性像のひとつだ。広告会社が、「戦争から平和」という時代の転換を宣伝(プロパガンダ)する像を建てた。つまり、政治に芸術を利用する点で、戦前との強い連続性がある。以後、平和を主題にした女性の裸像が全国で大量に建てられた。女性に特定のイメージを押しつける手法は、感情に訴えやすく、戦意高揚にも反戦にも利用しやすい。
ウクライナのマリウポリに、先日、ロシア軍を歓迎する高齢女性をモチーフにした「アーニャおばあさんの像」が建った。主張は対極的だが、「表現の不自由展」などで話題になった慰安婦を象徴する像は「平和の少女像」だ。/もちろん、女性表象の利用といっても、権力側のプロパガンダか、民衆の抵抗に呼応した切実なものかでは意味がまったく違う。政治色が強いから芸術的価値が低くなるわけでもない。/日本では「作者や作品は、政治や社会と無関係な、純粋なもの」という神話がこれまで強すぎた。表現の自由があるはずなのに、慰安婦だけでなく天皇制などタブー視される題材が少なくない。(そういう点からすると)ウクライナの芸術家を日本に招くといった支援の広まりは画期的だ。/しかし、イラク戦争など過去になぜ同様の支援が広まらなかったのかを問うたり、ロシアの侵略を過去の日本に重ねたりする思考は希薄だ。(その点)日外では、芸術家が金の出所に問題がある美術館や芸術支援財団をボイコットする動きなども広まつている。
作品を発表することは、必ず何らかの政治への加担である。「政治的ではない」と主張して作品を作るのも政治的態度だ。このことを肝に銘じておきたい。【聞き手・鈴木英生】
小田原さんの主な論点に下線を施してみた。この下線部をつないでいくと、小田原さんの言わんとすることの要点がつかめる。いくら「作者や作品は、政治や社会と無関係な、純粋なもの」と主張しても、それは明らかに間違っていて、どんな制作物でも作者の伝えたいメッセージは作品に込められているし、また見る側の見方で作品の解釈や主張もちがってとらえられる。要は、いったん制作物が出品されたら、あとは見る側に委ねられるのだ。
平和を象徴する「少女像」を展示することに権力の立場から反対し、鑑賞させないという日本維新の会の態度は、芸術のなんたるかを全く理解しない暴挙と言われても仕方ない。各界から指摘され、日を限定して大阪の「府立労働センター」で展示されたことにも反対し、「少女像」を設置したロサンゼル市当局との「友好都市」関係を破棄することを平気でした大阪の為政者=吉村知事の「暴力」も、《もっとも「政治的態度」》として、糾弾されねばならないのだ。
小田原氏のインタビューを聞き取った記者の「まとめ」に付けられた見出しにあるように、「政治性と無縁な作品はない」という、芸術作品の初歩的な理解すらしない「政治家」は、政治家の名に値しない。
1.コロナ禍でテレビの露出度最高を誇っているときの知事の顔と、「慰安婦問題」「IR問題」に言及している時の吉村知事の顔つきまで変わっていることに、視聴者はもっと敏感に気づくべきだろう。
○
以上3氏の論考。インタビュー記事を記録しながら、一定のコメントを加えてきた。三者三様の角度、芸術分野を取りあげていて、新聞社の姿勢が読者に伝わる構成になっている点で、この特集はよくできている。
ここまで記述してきて、私は「やはり音楽こそが、困難な局面であっても、ひとを勇気づけ、生きる力を与えるものだという考え」は、ますます強国なものになってきている。むろん音楽だけがということではない。コロナ禍にあって、私が足を運んできた「音楽演奏会場」「ライブノ`ウス」「芝居小屋(ミニ劇場)」「映画館」「美術館」等々は、どれほど私の気持ちを高め、生きる力を私自身に与えてくれたことか。(別紙に一欄を作成しておいたので参照ください)
そうした中にあっても、なんといっても「音楽」の力は、やはり大きいものがあると、言いたい。
そう思っているところに、少し前になるが、5月9日の毎日新間の夕刊に載った記事が出ていた。それを必要な個所にしぼって紹介したい。
今春東京芸術大学の学長を6年間務め、退任したバイオリン演奏家。指揮者である澤 和樹さんのインタビュー記事だ。見出しは「社会に音楽は必要不可欠」。
任期満了で退かれた澤氏は、音楽活動を本格化させる。演奏のみならず、指揮者としての取り組みにも意欲を見せる澤氏に、コロナ禍などと向き合った学長時代や今後の展望について聞いた、と前置きしている。
「まずはやっばり肩の荷が下りたというのが偽らぎる気持ちですね。本当にあっという間でした」。
就任から間もない頃、芸大生たちのユニークな姿を紹介した「最後の秘境 東京芸大」(二宮敦人著、新潮社)が刊行され、話題になった。「入試倍率は東大の3倍」「卒業後は行方不明者多数」という帯のキャッチコピーが印象的だったという。
「それもそうだな、と。でも、学長になったからには、そこを笑ってすませていてはいかんだろうなと思った」。芸術に対して、世間では浮世離れしたイメージは根強い、「どうすれば芸大で学んだ人たちが世の中に貢献できて、それが世の中から本当に必要なものとして受け入れられるか。それが、自分が学長である一番大きなミッションだと感じていた」と明かす。
その上で、「芸術家は大変だから、もっと予算をくださいと言っても我田引水の声にしか聞こえない。例えば経済界の人たちが、衰えてしまった日本の国の力を取り戻すには芸術やアートの力が必要だと言ってくれない限り、認められることはないだろうと思った」。学長として政財界との意見交換や企業経営者向けの講演のほか、メディアにも露出するようにしたという。
最後の2年間はコロナ禍に見舞われ、世間では「芸術は不要不急か」との議論が巻き起こった。「芸術は本当に大事なのか、と自間自答する、ある意味ではいい機会になったと思う」と語る。
「やっばり世の中からは、不要不急で片付けられていることも分かった。それではだめだろうということで、若手芸術家支援のクラウドファンディングを立ち上げたり、リアルな音楽会や展示会ができない中でもインターネット上で『東京芸大アートアェス」というバーチャルな芸術祭を開催したりした」。ネットでつながることで、学内ではこれまで乏しかった学部や研究科を超えた交流が図らずも活発になったという。
■ ■
学長時代も演奏活動は継続してきた。ピアニストの菱沼恵美子とのデュオは昨年、結成45周年を迎えた。弦楽四重奏団「澤カルテット」も30年以上、同じメンバーで続けている。学長退任と同時に教授職も退官し、今後は指揮者としての活動にも力を入れていく。
指揮者には子どもの頃から憧れていたという。大学2年から3年に進級する時には、指揮科への転科を考えたが、恩師の東儀祐二に相談したところ、「若いうちから始めるより、´バイオリンをやって、室内楽もやって、オーケストラも経験して、40歳くらいから始めた方がいい」とアドバイスされ、器楽演奏に集中。しかし、グストコンサートマスターなどで多くのオーケストラに参加し、指揮者の姿は近くにあった。「門前の小僧として、いい指揮者も、悪い指揮者も見てきた」と語る。
「音楽表現のツールとして、オーケストラは究極のもの。弦楽器奏者としての音作りのノウノ`ウとか、カルテットで4人の演奏家の気持ちを一つにして作っていくところの難しさも面白さも経験してきたから、それらを指揮活動でも生かせればと思う」。
(このように)演奏家として、指揮者として、音楽が社会に必要不可欠な存在であるというメッセージを投げかけていきたいと(結んだ)。
不明にして、私はバイオリン演奏家であり、指揮者である澤 和樹を知らなかった。学長職6年を終え、教授職も退任するというのだから、これからの人生はさらに演奏家・指揮者として存分に活動されることだろう。そのうち演奏会で面前の澤氏を見る機会があるかもしれない。それを楽しみにしている。
それにしても、スポーツほどには芸術への関心、支援は薄いと言わねばならないだろう。パソナが淡路島に企業の拠点を移し、西側に演芸場をつくり、西東三鬼を主人公とする演劇を舞台で展開してくれ、私たちを楽しませてくれた。パナソニックや電通あたりも、もっともっと芸術支援に乗り出していかないと。演芸場の責任者は、まだ30代かと思われる若い方だった。こうした思い切った起用が、やはリパソナの魅力なのだろう。
○
もう一人、5月25日の毎日新間に紹介された(「ひと人」欄で)芸術プロデューサー西尾智子さん(70)=西宮市=を取りあげよう。この方も初見である。福井県敦賀市出身。82年にカルチャーサロン「アプレ・ミディ」を結成。88年にバレエ公演を初プロデュース、92年に制作会社「ダンスウエスト」を設立し、バレエや古典芸能など数多くの舞台公演を手がける。こういう略歴の方だ。
お仕事は「芸術家同士の出会いを演出し、ステージ上で化学変化を起こす」舞台芸術の世界で「関西にこの人あり」と知られる名物プロデューサー。
若狭の旧家に生まれ、幼少期はピアノに日本舞踊、茶道に打ち込んだ。芸事が好きだった祖父にたびたび、京都へ歌舞伎に連れて行ってもらったという。…各界の専門家の話を聞くカルチャーサロンを始めると、外部からのイベント依頼が舞い込むようになる。/バレリーナー、森本由布子さんに出会い、磨き込まれた身体表現にほれ込んだのはその頃。しかし当時のバレエ界は東京一極集中で、関西のバレリーナーが活躍できる舞台がない。「ないなら作ればいい」とバレエ公演の制作に乗り出した。「失敗する」と言われたが、イベントで培った人脈から協力者も集まり、手売りで1200席が完売。だが、そこで満足せず「なんて面白いんだ」と身を乗り出したのがこの人の真骨頂。ジャンルを広げ、会社を設立。人が人を呼び、出会いを呼んでいく。
16歳の時の舞台を観て「こんな踊り、見たことがない」と衝撃をうけた熊川哲也さんには、英国から帰国する度に「ステージやらない?」とアタックし続け、1996年に熊川さん初のセルフプロデュース作品「MADE IN LONDON」を実現。日本バレー界のスターとして飛躍する礎を築いた。
2000年代からは、能楽観胆流の人間国宝、梅若六郎さん(現。桜雪)と二人三脚での舞台づくりに注力.古典の名作からバレエやコンテンポラリーダンス、日本舞踊など他ジャンルとの競演で能の新たな可能性を追求した。08年にロシアから招いたバレエ界の至宝、マイヤ・プリセッカヤさんと梅若さんが京都。上賀茂神社で舞った「ボレロ」は語り草。ギリシャの野外劇場やパリ。オペラコミック座で新作能を公演し、活躍は世界に広がる。
夢は「子どもたちに長い舞台を、ただで見せてあげられるようにすること」。バレエも能も見たことない学生も「一度でも本物を見せると、みんな『すごい!』と食いついてくる」という。
「本物は裏切らない」は、自身の原体験から得た信条でもある。(澤木政輝記者、大字は下橋)
○
東京芸大前学長、´バレエ公演、古典能とのコラボ舞台の演出家。お二人の芸術こそ人間になくてはならない栄養素という取り組みを前に、こうした声をどのように広げ、支えていくか、コロナ禍が明けたらではなく、ようやく収束の感じが濃厚になってきた今こそ、芸術分野のあらゆる動きに日配りしながら、そのわずかでもいいから自分で足を運ぶことをしていく、その刺激として、これまで記録・記述してきた。
(ここで一端閉じたのだが、ひと月近く前に切り抜いておいた記事がでてきたので、ここに追加しておく。
横見出しは@「新世界より」でウクライナ励ます 縦見出しで「チェルニヒウに戻る日待つ日本人指揮者」その日本人指揮者とは、チェルニヒウ・フィルハーモニー交響楽団常任指揮者、高谷光信さん(45)。=(民間のアパートが爆撃され燃えている映像がSNSで流れてきた。私が借りていたアパートだった)。
ロシア軍によるウクライナ侵攻の3日後、ウクライナ北部の都市チェルニヒウを拠点とする楽団の常任指揮者。高谷さんが日本から発信した一連のツイートは、大きな反響を呼んだ。戦争下で音楽家に何ができるのか。スラブ音楽を愛し、ウクライナで20年間活躍してきた日本人指揮者は、今何を思うのか。=(リード文)
一一音楽の世界にそれほど詳しくない私だが、高谷さんの年齢にまず驚いた。現在45歳、20年前は25歳。その経歴をみると、次のようだ。「高谷さんとキーウの出合いは高校時代。母校の堀川高校音楽科(現堀川音楽高校)がキーウ市立ルイセンコ音楽院と姉妹校だった。キーウの高校生と共演するうち、「いつかキーウに」と夢を抱いた。大阪音大卒業後、2000年、ウクライナ国立チャイコフスキー記念音楽院指揮科に入学。首席で卒業した。同院初の日本人卒業生だった。その後、チェルニヒウ。フィルの指揮者に就任。以来20年間、年に4~5回ウクライナに滞在し、これまでに120回を超える演奏会をこなしてきた。(まさに音楽は国境を越えるのだ。が、コロナ禍がその行く手を阻む)20年2月の演奏会以来、ウクライナに行けていない。高谷さんは今、フィルの仲間の身が案じられてならない。(楽団員のだれかが兵士として戦場となった場に赴いていないか、命は大丈夫なのか?)
首席指揮者のアンドレイさんとは今もショートメッセージを交わしている。高谷さんはスマホ画面にあるキリル文字のやりとりを記者(小国綾子)に和訳し、読み上げてくれた。
「ミツ、電気も水道も止まっている。街は爆撃された。家族は西側に逃がした。街の写真は送れない。なぜなら僕は軍隊に入り、街から離れた丘を守っているから」(下橋の予想があたった)アンドレイさんは指揮棒を銃に持ち替え、今もチェルニヒウにいるのだ。
忘れられない記憶がある。14年の年明け、高谷さんはフィルの団員は2月のチェルニヒウでの演奏会に向け、ドボルザーク交響曲第9番「新世界より」を練習していた。折しも市民のヤヌコヴィッチ政権批判が高まり、キーウの「独立広場」ではデモ隊と治安部隊が何度も衝突。予定していたキーウでの演奏会は中止。(ドボルザーク「新世界より」を私は何度聴いたことだろう。アメリカの指揮者・バーンスタインの指揮によるものだった。それを聴かないと眠りに就かない習慣となっていた。まだ現役真最中のことだった)
第4楽章に入った時、最年長のチェロ奏者が突然おいおいと声を上げて泣き始めた。高谷さんは驚き、演奏を止めた。すると彼は涙でしわくちゃの顔でこううめいた。「こうして……こうしてずっと音楽をしていたいんだよ」(ここを書き写している私は胸がつまり、容易にワープロをたたくことができない。涙のまま、それでもワープロをたたきつづける。これまでにもこういうことがあったか。涙で水洟がでてくるのを抑えながら書き続けることができるか)
再び第4楽章を通した。気迫のこもった音がした。演奏を終えた時、誰もが目を真っ赤にして泣いていた。
「僕も1ミリも動けませんでした」。クリミア危機が勃発したのは、演奏会から約半月後のことだった。
「ずっと音楽をしていたいんだよ」。あの声が今も高谷さんの耳を離れない。(音楽の指揮者も、演奏者も、武器でなく楽器を手にと、心の中で叫びながら、ある楽団員は戦場に赴いているのだろう。戦争はひとの命を奪う。切迫した中での演奏途中で、最年長の楽団員が大泣きした、そこに音楽を愛する演奏家。指揮者たちの思いが凝縮されている。平和でなければ音楽を人々に届けることができない。)
(記事はここで「ロシアを憎まず」という見出しをつけ、記事をつづけている)
一―今回の戦争は音楽界にも影を落とす。欧米ではプーチン大統領と親しい音楽家たちが職を追われた。日本国内むもロシア軍の戦勝がテーマのチャイコフスキーの大序曲「1812年」のプログラムの変更が続く。高谷さんも「この状況下でこの曲をあえて演奏することはない」と納得している。
しかし、(高谷さんは)もしもロシア人作曲家の作品全体を忌避するような動きが起きた時は、全力であらがおうと決めている。「僕はスラブ音楽を愛する音楽家として、戦争は憎むが、ロシア人は憎まない。両国とも平和になってほしい。これからもロシアの作品を指揮していく。チャイコフスキーやラフマニノフを。ウクライナで学んだスラブ音楽の魂を日本に伝えるのが僕の役割だから」(波線は下橋)
日本ではプロやアマチュアのオークストラや合唱団の指揮をする傍ら、大阪芸大などで教えている高谷さん。日本とウクライナの交流を目指し21年に設立した「日本ウクライナ音楽協会」を母体に、音楽での支援を考えている。
「日本へのウクライナ避難民の中で楽器ができる人がいたら一緒に演奏する機会をつくりたい。ウクライナ支援のチャリティーコンサートも実現したい。停戦が適えばウクライナの地で日本との音楽交流を目指したジャパンフェスティバルを開きたい」と意気込む高谷さんだ。
さらに高谷さんは、つづけて語る。「僕がウクライナで学んだスラブ音楽の本質は、《自由》です。苦難の歴史の中で、何度も言葉を奪われた。長く国家の独立がかなわなかった。そんな土地だからこそ、人々には『我々は自由の民である』という強い信念がある。自由への希求が、音楽の中にも息づいているんです」
このウクライナ人の苦悩を日本にひきすえると、沖縄。奄美のウチナンチューや北海道のアイヌ民族の苦難の歴史と部分的にかさなる。その地の音楽は、独特の音色・哀調をおびている。
高谷さんは、いつかチェルニヒウで演奏ができる日が来たら、最初に演奏するのはドボルザークの「新世界より」と心に決めている。「僕らはどんな時もあの曲を演奏してきた。クリミア危機の時も。自由を謳歌できる新しい世界。そして故郷を思う作品だから。あの作品でウクライナに観客たちを励ましたい。その日が来るまで、僕は日本でできることをやろうと思います」高谷さんの心に秘めたこの思いが、やがて実現することを強く願わずにはいられない。
5月25日の毎日新聞の特集ワイドで、上東麻子記者が元国連事務次長の明石康さんにインタビューした。
彼は語りの後半で次のように指摘する。
一一日本では、この侵攻を契機に「ロシアは悪でウクライナは善」という単純な構図で語られがちだが、「もちろんロシアの侵攻行為は非難されるべきです。でも、ロシアという国がすべて黒でウクライナがすべて白だという極端な見方には異論があります。どの国もグレーなのです」。そもそも国際関係を保つうえで、国の価値を他国が判断すべきでなはないと。「考えが違っても正面からぶつからないように、お互いを尊重する。専制的な支配の国でも暴走せず、市民が平和に暮らせることが何より大切ですから」と。(波線は下橋)
難しい局面のかじ取りを長年やってきた明石さんの言は重い。ここに立ちどまって考えを深めていきたい。
2022・6・3脱稿 引用・記述 下橋 邦彦
*若い45歳の指揮者高谷さんの記事を小国記者がまとめられた。それを長く引用しながら、ポイントになる個所を強調線で示した。ここに、もう一つ加えたい記事がある。6月6日の毎日新聞夕刊で紹介された「活動60周年 ウクライナ侵攻に思い複雑」という見出しが目に入ってきたのだ。
バイオリニスト・前橋汀子さんに須藤唯哉記者がその思いを聞き取った記事だ。音楽愛好者でなくてもその名は知っている前橋さんだ。1日ソ連や米国への留学を経て、ソリストとして第一線で走り続ける前橋さんにこれまでの歩みやロシアによるウクライナ侵攻での分断が進む世界情勢について何を思うのか、話をきいた。
==(記者の問いかけに対しインタビュー中)前橋さんの国からは往年の音楽家たちの名前が次々と出てきた。
オイストラフ、ワイマン、シゲテイ、 ミルンテイン、ストコフスキー…。「今、考えるとみんな素晴らしい出会いだった。計画したことではなくて、魅力を感じた人たちがたまたまそこに住んでいたから訪ねて、結果的にいろんな国に行くことになった」と明かす。/そんな出会いに支えられながら、演奏家としての道を切り開いてきた。「ソリストとして、まさかこんなに長くステージに立って、みなさんに聴いていただける機会を設けられたことは本当にありがたい」
■ ■
旧ソ連に渡ったのは、東西冷戦時代だった17歳の時。レニングラード音楽院創立100年記念の一環として、日本人初の留学生に選ばれる。「よくぞあの時代に行ったなと改めて思う」留学中、夏体みには著名な音楽家を多数輩出した都市オデッサを訪れるなど、ウクライナにも足を運んだ。それだけに、ウクライナ侵攻によってロシアの作品や音楽家たちが排斥される現状には、複雑な感情を抱く。「なんて言ったらいいか正直わからない。それぞれの事情があるから大変難しい問題かもしれないけれど、少なくとも音楽には国境はない」と、言葉を絞り出した。/一方で、歴史に名を刻んだ作曲家たちの作品は、これからも演奏されるべきだ。「チヤイコフスキーやラフマニノフが聴けなくなるなんて、こんなに悲しいことはない。ロシアの音楽がこれだけ時間がたっても人の心を打つことを考えたら、やはり何らかの形で演奏できる機会を作り続けるべきだと思う」と、力を込めた。
■ ■
今月(6月)、60周年記念と銘打った公演を控える。プログラムのメインにはベートーヴェンのソナタ「春」や「クロイツェル」を据える。記念CDもリリースし、オークストラ・アンサンブル金沢との収録曲や、やはリベートーヴェンの協奏曲と小品だ。「ベートーヴェンは人によって感じ方が仝然違うと思う。今まで数えきれないくらい演奏してきたが、今回弾くにあたって改めて、新たな気づきや試したいことが多々あるので、『また弾く』という感覚はない」と言い切った。演奏家として、これからも走り続ける。「気力が続く限リバイオリンでの探求を続けていきたい。これで終わりということはないですから」と笑顔を見せたという==。
大阪のザ・シンフォニーホールは、今月12日(土)。
演奏家として60周年記念を迎えてなおこの旺盛な意欲には、頭が下がる。そうなのだ、「これで終点」と思えば、そこで止まってしまう。どこまでも「探求」を続けていくことで、今日の前橋さんのバイオリン演奏があるのだ。実は、私はまだ前橋さんの演奏会に足を運んだことがない。この機会にできれば会場に出かけたい。
(前橋汀子のプロフィール)
1943年1月11日、東京に生まれる。ニューヨークから渡欧。シゲティやミルシティンに師事し、薫陶を受け
る。シゲティがあまり関心を持たなかったチャイコフスキーなどの曲に強く関心をもち、あらたな解釈をして
いったと言われる。最晩年のチャップリンなどと親交を結んだ。
辻久子さん亡き後、まだ80歳になっていない前橋汀子の今後の活躍に大いに期待したい。
2022・6。7補足 しもはしくにひこ
お問い合わせはコチラへ!
![]() 電話: 090-5256-6677
電話: 090-5256-6677
![]() E-mail:sonen1939@s4.dion.ne.jp
E-mail:sonen1939@s4.dion.ne.jp
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。